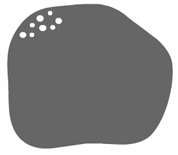Teori
温故知新 作務衣(さむえ)製作22作
・自分で織った手織りの作務衣です。
2012年12月頃から、手織り教室に通いました。(約5年間。)
自分で生地を織ろうと思ったのが動機です。
自分で織れば、自分の思った色合い、風合いが出せる。
一応、やるだけは、やろう。
そうしなければ、自分自身が、満足できないのではないかと
思ったのが一番の理由です。
教室に通うため先生に連絡しまして、面談です。
記憶では、最初に『先生、野良着を作りたいのです。』と話したら、
少し驚かれていたのを覚えています。
そうですよね、突然、野良着を作りたーい。ですから。 🙂
驚くと思います。
先生は、ご高齢ですが、
素敵な手織り服を着ていたのを覚えてます。
その手織りを見たときに、はじめて布の個性というか
布の力というものを感じました。
この時、もう一度、自分が作りたい作務衣は、どんな作務衣か?
再認識していました。
私の中では、襤褸(ぼろ)の美、
野良着、朽ちていく布、それでも存在感がある布。
うまく言えませんが、侘・寂(わび・さび)というか、
枯れたというか、一言では言えない布です。
あくまで、私の想像です。
具体的にはどんな布なのかは、自分でも整理がついていません。
そんな、訳の分からない布を目指していたようです。
教室に参加すると、初歩のストール作りです。
綿糸も絹糸等、最初は、その特性を理解できません。
織り機の操作もわかりませんが、糸を通して、教えてもらいます。
手と足を使って、誰でもトントン、トントンと織り上がっていきます。
昔話の鶴の恩返し状態です。 🙂
何回か通うと織りがります。
最初は、感動です。
⇒はじめて、できたストール。
ストール完成後、2回目の手織り布が、この作務衣です。
9メートルを織りあげました。
最初の頃は、糸の用意もありませんので、教室の糸を
使いました、赤い糸があったのでそれを使用。
もし、赤い糸がなければこの作務衣は、できていません。
作務衣にするための、縫製も手織り布になると少し変わります。
布の始末が大事です。糸がスルスルと抜けるため
抜けないようにシッカリとミシンで仕上げてもらいます。
作務衣の裏地は、無地の木綿です。
3月に近いころから織りはじめ、ずいぶん時間がかかったのを
覚えています。
コツコツと忍耐で9メートルの手織りの生地です。
3ヶ月ぐらいかかったでしょうか?
時に経糸が切れたり、緯糸を頻繁に変えたり
9メートルは、長いー。でも、最後は、感動。
織続けた後は、達成感があります。
反物になったのが、2013.7.13でした。
1枚の手織り布が、作務衣になりました。
この作務衣は、いまだに着ています。
自分で作ったものは、思いがあります。
着ていて眺めると、この辺を織っていた時は、
緯糸に迷っていたとか、
この経糸は良かったとか、織りが緩いとか、
着ながら反省することもあります。
そこが、いいところです。
手織りは、美しい。
今思えば、よくやった。五十の手習いです。 😆