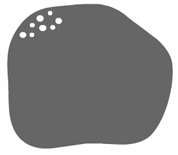Teori
温故知新 作務衣(さむえ)製作30作
・綿紬でこだわりをもって製作した裂き織り作務衣
ここにきて、挑戦したのは、
渋い作務衣、重厚感、存在感です。
少し気合をいれて、
綿紬の布玉をかなりの量と種類つくります。
これが30枚目の作務衣です。
60枚を目標にしてきました、ようやく半分です。 🙂
ゴツゴツ感のある裂き織りで仕上げてみたいと思い、
糸も太めのカスリで整形します。
今回は、反物の最初から最後までが、
同じトーンで仕上げるということを、
念頭にいれて始めます。
ほとんど、目だった縞がない状態を目指します。
すべて同一の綿紬の裂き織りです。
真剣そのものの私を後ろから、写真を撮る嫁さん。
邪魔しないで欲しい。
数を間違いそうだからほっといて欲しい。 


今回の糸は、糸のきんしょう の
【17/2シルク紬カスリ(モノトーン)】上質な絹で
しっとりやわらかく、ほのかな光沢のある糸です。

自作で糸を立てる台を作成したら
作業が少し楽になりました。

整形後、糸を通します。太目のカスリの絹糸です。
順番を変えてアクセントで入れます。

織り始めます。

トントン、トントンとシッカリと織り込んでいきます。
裂き織りの場合、布玉作りに根気がいります。
裂く布が大量にあるのならのんびり作ればいいのですが、
裂く布が限られている場合、1着分に足りるかどうかは、
最初には、わかりません。
カッターで布を切りますが、切る布の幅も
調整が必要です。
織りこむ布の量を睨みながら、足りる?足りない?
を判断しながら進めます。
全体をみながら色使いをする必要があります。
もし、途中で裂く布がなくなったら
新しい柄になり全体の統一感がなくなります。
目指している理想の無地グラデーションの反物は
できなくなります。
最初から最後まで一貫して同じパターンで
仕上げていかないといけません。

何とか、同じトーンで仕上げているつもりです。
なかなかいい。(自画自賛) 😎
今回の綿紬も生地がしっかりしていて、
手で裂くことができませんのでいつものように
サークルカッターを使用して布を切りました。
どんな布もたて糸とよこ糸でできています。
水平、垂直に織ってあります。
綿紬の生地をカッターで切る時、多少のズレで斜めになると
その分、布玉がポロポロとフサのようになります。
織る場合も、綿紬は、しっかり織り込まないとしっくりと
馴染んできません。
スカスカと隙間があいてしまいます。
シッカリ、トントンと強く織り込まないと、
布になりません。
なかなか、手がかかり、注意も必要です。

シッカリ織ってあります。
良く詰まっています。
![]()




作務衣になったらなかなか、良くなりました。
この一着は、色使い、生地ともに
苦労しましたが、勉強になりました。
渾身の一着です。