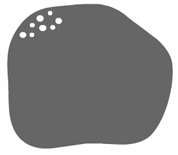Teori
温故知新 作務衣(さむえ)製作12作
・着ていておかしいことに気が付いた作務衣(さむえ)作り。
なんか違うと思ったのは、着ているうちに
少し、ペタンと見える、着心地がしっくりこない。
何ども着ては、脱いでを繰り返してようやく気が付いたのが、
前身ごろのかぶさりの違和感。
最初は、気が付かなったけれど着ているうちに
なんとなくぎこちない。
作務衣に限らず、服って難しいですよね。
人それぞれ、体型が異なります。
体型もサイズだけの問題でなく、
手が長い、首が短い、お腹だけポッコリとか、
服のサイズのS、M、L、XLだけでは収まるはずは、ありません。
一人ひとりが特別サイズです。
最初に型を製作した縫製会社に
再度修正依頼を考えましたが、やっぱり心機一転。
個人のパタンナーさんを新しく紹介頂いて
訪問することになりました。
確か、まだ暑い季節だったと思います。
自宅兼仕事場ということで、『ピンポーン』と
ベルを鳴らしましたら、私より少し年配の男性の方が
出てきて、『よろしくお願いします』と挨拶いただき、
ドラフターなるもので、型紙をつくる説明を受けました。
持参した作務衣をもっていき、細かい指示書をもとに
実際に私が着てみます。
しばらく眺めて、この辺がこうですね、ここがこうですねと、
ポイント的に服を詰めたりしながら、修正していきます。
おじさん二人が服を着たり脱いだり、客観的には、
おかしな光景ですが、必死です。
結論としてシルエット修正の一番のポイントは、
背中の首回りです。襟ぐりが美しく仕上がっていなかったので
そこを変更したら良くなりました。
胸のあたりの襟の開き角度も修正。
パターン代金は、新規作成に関わらず、縫製会社の半額以下でした。
写真をみると襟が立ち上がっています。
襟幅の変更や前身ごろにおくみをつけて仕上がりです。
このような仕上がりにすることで生地が節約できることと、
反物で作務衣が作れることがわかりました。
一歩先進です。
とりあえず、新しい型で作るため、生地を用意して製作。
まとめ:新しい作務衣の型は、襟が立ち上がっています。
この一枚は、今も最新の型として製作に役立っています。
イエローの裏地は、肩裏だけですが、これで十分かもしれません。